この楽曲は、自己理解への深い問いかけと、過去の経験、特に迷いや挫折が現在の自分をどのように形成しているのかを探求する内省的な旅を描いています。タイトルにもなっている「僕にはどうしてわかるんだろう」というフレーズは、明確な答えを求めるのではなく、自己を探求し続けるプロセスそのものの不確かさと、その中に見出す微かな気づきの瞬間を象徴していると言えるでしょう。
1. 自己認識への目覚め:日常の変化と内面のざわめき
歌詞は、日常の風景に小さな変化を加えることから始まります。「今晩は降りる駅を変え」「今晩は歩く道を変え」という行動は、単なる気まぐれではなく、自身の内面と向き合うための意図的なきっかけ作りと解釈できます。普段と違う道筋を辿ることで、意識は日常のルーティンから解放され、内省へと向かいます。
その過程で主人公は、かつて心の中にあった「小さなプライド」の存在を意識します。それは、失われた自信や、過去に抱いていた理想の断片かもしれません。しかし、その「行方」や「香り」を辿ろうとしても、すぐには見つけられません。むしろ、自己認識の決定的な瞬間は、予期せぬ形で訪れます。「あの聴きなれたリリックで涙を流し出すまで」、彼は自分の心の奥底にある感情に気づけずにいました。音楽という外部からの刺激が、無意識の領域に触れ、抑圧されていた感情を呼び覚ましたのです。これは、自己理解が論理的な思考だけで到達できるものではなく、感情的な共鳴や直感的な気づきによってもたらされることを示唆しています。
2. 過去の経験と自己形成:「僕をつくってる」もの
歌詞の中で繰り返される「僕以上に、僕以前に、僕よりも 僕のことつくってる」というフレーズは、この楽曲の核心的なメッセージの一つです。これは、現在の自分という存在が、自分の意識や努力だけで成り立っているのではなく、自身ではコントロールできない過去の経験や、無意識の記憶、さらには他者との関係性といった、より広範な要素によって形作られているという認識を示しています。
特に、「迷える日々」や「挫折の日々」といったネガティブに捉えられがちな過去の経験が、現在の自己認識において重要な意味を持っていると歌われます。「迷える日々」は、振り返れば「これとない味のエッセイ」となり、人生に深みを与える独自の物語となります。「挫折の日々」は、当初は色を失った「全部モノクロ」の世界に見えたかもしれませんが、それは未来において豊かな「色づくため」の準備期間であったと肯定的に再解釈されます。悲しみや困難さえも、自己を形成する上で不可欠な要素であり、それらを乗り越えようとする過程(「言い訳を探して目をそらしてみようが」「悲しみは言い訳の数で目を閉ざしてみようが」)も含めて、自分自身を形作ってきたのだと受け入れています。
3. モチーフ:「モノクロ」の意味合いの変遷
この歌詞において、「モノクロ」という単語は非常に重要なモチーフとして機能し、その意味合いは曲の進行とともに変化していきます。
- 初期の「モノクロ」:挫折と喪失の象徴 最初に登場する「全部モノクロ」は、「挫折の日々」と結びつけられ、希望や色彩を失った辛い時期、感情が停滞し、未来が見えない状態を象徴しています。喜びや感動といった鮮やかな色彩が感じられない、平板で厳しい現実認識を表していると言えるでしょう。
- 中盤の「モノクロ」:葛藤と変容のプロセス Bridge部分では、「モノクロは焦シアン蒼白へ」と表現されます。ここでは、単なる無彩色ではない、より複雑で生々しい感情の色合いが示唆されています。「焦げ付くような青(シアン)」や「血の気を失った白(蒼白)」といった表現は、真夏の荒れた天気や海の神といったイメージと重なり、激しい感情の葛藤や苦悩、あるいは精神的な消耗を表している可能性があります。モノクロが、単なる色の欠如ではなく、痛みを伴う変容のプロセスを経ていることを示唆しています。
- 終盤の「モノクロ」:記憶と現在を結ぶ豊かな色彩 楽曲の終盤に至ると、「モノクロ」の意味合いはさらに深まります。「色で満ちていたモノクロ」「思い出すためのモノクロ」という表現は、一見矛盾しているように見えますが、過去の記憶に対する現在の視点を示しています。過去の出来事そのものは、辛く色褪せて見えた「モノクロ」の時期であったとしても、現在の視点から振り返るとき、そこには様々な感情、経験、学びといった豊かな「色」が満ちていたことに気づくのです。そして、その「モノクロ」の記憶は、現在の自分を理解し、未来へと進むために「思い出す」べき、かけがえのない財産となります。つまり、「モノクロ」は、単なる過去の象徴ではなく、現在の豊かさの源泉であり、自己理解のための重要な参照点として、肯定的な意味合いを帯びるようになるのです。
4. 経験の昇華と未来への視座:翡翠の軌跡
過去の経験は、「走馬灯、胸に残っている」と表現され、断片的な記憶が現在の感情と結びつき、自己理解を深める手がかりとなります。「あの港から光を手繰ってここまで来たんだ」という一節は、困難な状況(港=出発点、あるいは苦境)から希望(光)を見出し、それを頼りに現在地まで歩んできた道のりを肯定的に捉えています。
そして、「僕たちは、翡翠の軌跡を生きている」という印象的なフレーズが登場します。翡翠は、古来より価値あるもの、深い緑色、そして時を経ても変わらない美しさを持つ宝石として知られています。ここでの「翡翠の軌跡」とは、迷いや挫折を含んだ過去から現在、そして未来へと続く、価値ある人生の歩みそのものを指しているのではないでしょうか。たとえ「モノクロ」に見えた時期があったとしても、その全てが緑豊かな翡翠のように、固有の価値と輝きを持っているのだというメッセージが込められています。
最終的に、「まるで明くる前のよう」という言葉で締めくくられます。これは、過去の全ての経験を受け入れ、自己理解を深めた先に訪れる、新たな始まりや未来への希望を示唆しています。夜明け前の静けさと期待感のように、これまでの内省の旅が、次なるステップへのエネルギーとなっていることを感じさせます。
結論:「どうしてわかるんだろう」の答え
結局のところ、歌詞は「僕にはどうしてわかるんだろう」という問いに対する明確な一つの答えを提示しません。むしろ、自己理解とは、過去を振り返り、その意味を問い続け、時に感情の波に揺さぶられながら、「モノクロ」の景色の中に豊かな色彩を見出していく、終わりなきプロセスそのものであることを示唆しています。迷い、挫折、悲しみといった全ての経験が、現在の自分を形作り、未来を照らす「翡翠の軌跡」の一部となる。その連続性の中に、自己理解の手がかりが散りばめられている、という深い洞察を与えてくれる楽曲です。
肯定的なニュアンスの単語: 咲いていた, 気づけなかったんだ(気づき), 言い訳探して(自己理解への過程), つくってる, わかるんだろう(探求), 味のエッセイ, 色づくため, 撒いていた, 香り, 辿った, 光を手繰って, 来たんだ, 聞いていた, 翡翠の軌跡, 生きている, 残っている, 色で満ちていた, 明くる前のよう, 思い出すため
否定的なニュアンスの単語: 降りる駅を変え(変化への不安), 小さなプライド(喪失感), 行方を探した(迷い), ずっと気づけなかったんだ, どうにも, 涙を流し出す, 目をそらしてみようが, 僕以前に(過去の否定), 迷える日々, 挫折の日々, 全部モノクロ, 歩く道を変え(変化への不安), 言葉足らず, 見失う, 悲しみ, 言い訳の数, 目を閉ざしてみようが, 荒天, 海神, 蒼炎, 骨相青に溶け, 焦シアン蒼白へ
歌詞に沿ったストーリー(80字程度): 見失ったプライドを探し涙した。迷いと挫折の日々はモノクロだったが、悲しみを越え、過去の光を手繰り寄せた。色で満ちたモノクロの記憶は翡翠の軌跡となり、まるで夜が明くる前のようだ。

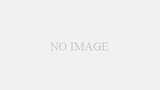
コメント