この楽曲は、単純な二元論では割り切れない複雑な感情や状況、そしてその中で真実を探求しようとする人間の姿を描いています。タイトルであり、歌詞全体を貫くモチーフでもある「Black and White」は、単なる白と黒、善と悪といった対立構造を示すだけでなく、それらが混ざり合い、境界が曖昧になった状態、すなわち人間の心の機微や世界の複雑性を象徴していると考えられます。
1. 探求への誘いと内なる葛藤
1.1. 謎めいた瞳と探求心の目覚め
歌詞は「愛して 満たして」という強い欲求から始まります。しかし、すぐに「入り混ざる black and white」というフレーズが続き、その欲求が単純なものではないことを示唆します。特に印象的なのは「覗き込んだその瞳は 解き明かす謎の虜」という部分です。これは、対象となる人物(あるいは状況)が持つ複雑さや神秘性に強く惹かれ、その本質や真実を知りたいという抗いがたい衝動に駆られている状態を表しています。瞳は心の窓とも言われますが、その奥にある「謎」に魅了され、まるで探偵が難事件に挑むかのように、あるいは恋する相手の心を探るかのように、解き明かしたいという欲求の「虜」になっているのです。
1.2. 感情の交錯:信頼、干渉、愛憎
人間関係、特に深い関わりにおいては、「信頼」だけでなく、時に過剰な「干渉」や、愛と憎しみが裏表になった「愛憎」といった、相反する感情が同時に存在します。「どんな言葉がいいだろう」という問いかけは、これらの複雑に絡み合った感情を的確に表現する言葉が見つからない、あるいは、どの側面を肯定し、どの側面を否定すれば良いのか判断がつかない、という戸惑いを表しています。「かすむ感情」や「未曾有の感覚」は、これまでに経験したことのない、理屈では説明できないような心の動きに翻弄されている様子を示唆しています。既存の「方程式(rule)」からはみ出し、自らを未知の「真実(truth)」へと導こうとする、制御不能な感情のうねりが感じられます。
1.3. 理性と本能のせめぎ合い
「ああしたい こうしたい あぁじれったい」というフレーズは、頭で考えた理想や計画(理屈)と、心の奥底から湧き上がる衝動や感情(本能)との間で揺れ動く、もどかしさを率直に表現しています。理屈で相手を説得しようとしたり、状況をコントロールしようとしたりしても、感情が先走って「から回って」しまう。それでも、表面上は「何ともない顔」を取り繕いながら、内面では必死に「試行錯誤」を繰り返しているのです。この、ちぐはぐで不器用ながらも真剣な態度は、傍から見れば滑稽かもしれませんが、本人にとっては切実な探求の過程であり、その人「らしい」個性として映るのかもしれません。
2. 曖昧さとの対峙:混濁する世界
2.1. 白黒つけられない現実:「嗅ぎ分ける black and white」
再び現れる「black and white」は、ここでは「嗅ぎ分ける」という動詞と共に用いられています。これは、白と黒が単純に分かれているのではなく、複雑に「入り混ざ」り、その境界線が曖昧になっている中で、鋭い感覚を研ぎ澄ませて本質や真実を見極めようとする意志を表しています。それは、単純な正誤判断ではなく、混濁した状況の中から、微かな違いや本質的な要素を嗅ぎ取るような、より繊介で直感的な作業です。「愛して 壊して」という対照的な動詞は、この嗅ぎ分けるプロセスが、対象への深い愛情と、同時に既存の関係性や固定観念を破壊するような激しさを伴うことを示唆しています。
2.2. 複雑系の迷宮:「絡み合う糸」と「歪な点と線」
世界や人間関係は、一本の単純な線ではなく、「絡み合ういくつもの糸」のように複雑に構成されています。その糸を一本一本「手繰って」、ぼやけていた焦点(ピント)を合わせようと試みる。しかし、見えてくるのは整然とした図形ではなく、「歪な 点と線」が繋がった「迷路」のようなものです。これは、真実への道筋が直線的ではなく、矛盾や不完全さを内包した、複雑で入り組んだものであることを示しています。この迷路の中で、再び「覗き込んだ瞳」は「謎の虜」となり、探求を続けることを余儀なくされます。
2.3. 深層心理の吐露:英語パートに見る葛藤
中盤の英語パートは、この探求に伴う内面的な苦悩や葛藤をより直接的に表現しています。「どうしてここに迷い込んだのか分からない」「真実を吐き出すのは苦しい」「嘘を見抜くのは不可能に近い」「あまりにも自然に感じるから」といった言葉は、混乱し、真実と嘘の境界さえ曖昧になった状況で、それでも答えを追い求めざるを得ない衝動(ハイスピードで)と、その一方で「本当に知りたいのだろうか?」という真実を知ることへの恐れやためらいが描かれています。切り抜けた先に何があるのか分からない不安と期待が入り混じった、不安定な心理状態が垣間見えます。
3. 矛盾の受容と未来への意志
3.1. 割り切れない想い:「仕様もない」「嫌いじゃない」
探求の過程で、理性では「仕様もない」と呆れるような、あるいは「興味ない」と突き放したいような感情や状況に直面します。それは、論理的に説明できない「こじつけ」のようなものかもしれません。しかし、それを「吐き捨て」て完全に拒絶することはできず、むしろどこかで惹かれ、「たった一つだけ 縋りついて」しまう。そして、その複雑さや矛盾に「染まったって 嫌いじゃない」と、ある種の諦観と共に、その曖昧さ自体を受け入れ始めている心境がうかがえます。白黒つけられないグレーな状態、矛盾を抱えた自分自身や相手、状況に対して、否定しきれない肯定的な感情が芽生えているのです。
3.2. 不安定な世界認識:「螺旋の中」「アンステイブルなピクセル」
「螺旋の中」という表現は、同じような状況を繰り返しながらも、少しずつ上昇または下降していくような、終わりが見えない探求の様子を想起させます。「勘繰った世界」は疑心暗鬼や不確かさを、「正誤の狭間」は判断の難しさを示しています。「アンステイブルなピクセルのフュージョン」は、デジタル画像のように、不安定で変化しやすく、部分的な情報(潜んだヒント)によって全体の解釈が「組み変わる」ような、流動的で捉えどころのない世界の認識を表していると言えるでしょう。
3.3. 結論:謎の向こう側へ
最終的に、再び「愛して 満たして」「入り混ざる black and white」「覗き込んだその瞳は 解き明かす謎の虜」という冒頭と同じフレーズが繰り返されます。これは、探求が終わったのではなく、むしろこの複雑で曖昧な世界と向き合い続ける覚悟が決まったことを示しているのではないでしょうか。「愛して 壊して」というプロセスを経て、「歪な 点と線を繋いだ この迷路」を進むことを受け入れ、なおも「解き明かす 謎の虜」であり続ける。そして、その「謎の向こう」にある、まだ見ぬ何かを「掴み行く」という強い意志を持って、物語は締めくくられます。
モチーフ「Black and White」の考察
この歌詞における「Black and White」は、単なる対立概念(善/悪、真実/嘘、愛/憎)として存在するだけでなく、それらが不可分に「入り混ざる」状態こそが、人間や世界のリアルな姿であるという核心的なテーマを体現しています。
当初、語り手は物事を白か黒か、明確に割り切りたい、理解したいという欲求(方程式、理屈)を持っているように見えます。しかし、探求を進めるうちに、現実はもっと複雑で曖昧であり、「black and white」が混濁した状態(かすむ感情、歪な点と線、アンステイブルなピクセル)であることを認識していきます。
重要なのは、「嗅ぎ分ける」という行為です。これは、白と黒を完全に分離することではなく、混ざり合った状態の中から、直感や鋭い感覚で本質的な何かを感じ取ろうとする試みです。それは困難で、「迷路」に迷い込むようなものであり、時には既存の価値観を「壊して」しまうほどの激しさを伴います。
しかし、最終的に語り手は、この「入り混ざる black and white」な状態を、否定すべきものではなく、むしろ受け入れるべき現実として捉え直しているように見えます。「染まったって 嫌いじゃない」という言葉は、その象徴です。白黒つけられない曖昧さ、矛盾を抱えた複雑さこそが、人間や世界の深みであり、魅力でもある。その「謎」に惹かれ、探求し続けること自体に意味を見出しているのです。
したがって、「Black and White」というモチーフは、単純な二元論への疑問提示であり、世界の複雑性と曖昧さの象徴であり、そしてその中で真実を探求し続ける人間の意志を表す、多層的な意味を持つ言葉として機能していると言えるでしょう。
肯定的なニュアンスの単語: 愛して、満たして、信頼、真実(truth)、導かせていく、冴える、ビジョン、縋りついて、嫌いじゃない、愛して、満たして、愛して、手繰って、定める、繋いだ、掴み行く、answers、ヒント
否定的なニュアンスの単語: 入り混ざる、かすむ、はみ出していく、じれったい、から回って、壊して、絡み合う、歪な、迷路、虜、干渉、愛憎、ひずむ、停滞する、仕様もない、興味ない、遮れない、こじつけ、吐き捨て、ひけらかして、染まったって、lost、coughing out、dusty、lies、Impossible、chasing、螺旋、勘繰った、狭間、固唾飲み込む、アンステイブルな、潜んだ
ストーリー(80字以内): 入り混じる白と黒の世界で、歪な迷路に迷い込む。愛憎や信頼が絡み合い、真実を求めて試行錯誤するが、から回る。矛盾に染まっても嫌いじゃない。謎の虜となり、その向こうを掴みに行く。

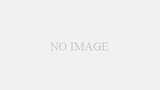
コメント